人に親切にすることで恩恵が廻ってくる
とある研究結果において、日頃から他人に親切をしている人は「自分は幸福だ」と感じやすく、さらにストレスを感じにくく、心と身体も健康であるという報告がされています。
「人に親切にしよう」と言われるとボランティア活動をイメージする人も多く、さらにボランティア活動は自己犠牲であるという考え方もあります。
ですが単純に、人に親切にしていればいつか自分にもたくさんの恩恵が廻ってくるという意味なのです。
研究者であり哲学者でもあるスティーブン・ポスト教授は、Big Thinkという動画サイトにおいて「他人を助けることで自分が助けられる」と説いています。
スティーブン・ポスト氏の研究によると、ボランティア活動をしている人は、幸せと健康を強く感じる傾向にあるということが証明されています。
ふだんの生活の中で「今よりも親切」を意識する
スティーブン・ポスト氏は、ボランティア活動を強調しているワケではありません。
要するに、ふだんの生活の中で今より親切になれるよう意識しながら生活することで、その人助けした恩恵が廻り廻って自分に返ってきますよ、ということを言っているのです。
わざわざボランティア活動に参加する必要はなく、ただいつものライフスタイルの中で親切できるように努力することを推奨しています。
生活はもとより、スケジュールや人生を変えることなく、ただ自分が親切にできる場を見つけるだけでいいということでしょう。
仕事やプライベート、家事など、ふとした瞬間に誰かが助けてくれるとすごく嬉しく感じたり、安心感を得られたり、沈んでいた心が楽になったりしたことがあるはずです。
大掛かりな親切をしろと言っているワケではなく、皆のためにほんの小さな親切を積み重ねていけばよいのです。
他人に親切をして見返りを期待するのではなく、ただ純粋に人助けするという行為は、実際には自分の心や身体に良い影響を与えているのだという人間の隠れた本能を説明しています。
そしてそれを実行すれば、窮地に立たされても乗り越える回復力が培われ、多くの恩恵を受けることで幸せに繋げていけるという考え方です。
日本のことわざ「情けは人の為ならず」
実は、スティーブン・ポスト氏のこの考え方は、「情けは人の為ならず」という日本のことわざとほぼ同じことを意味していることにお気づきでしょうか。
「人に情けをかけることはその人の為ではなく自分の為である=巡り巡って自分に良いことが返ってくる」という意味となります。
実際には「人に情けをかけるとその人のためにならないからやめておけ」という間違った解釈で覚えている人も多いので、今ここで再確認しておきましょう。
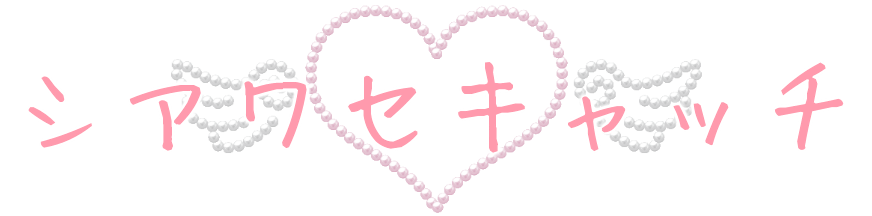
discount enclomiphene generic is good
get enclomiphene generic sale
kamagra comparer les prix cvs
sans ordonnance kamagra prescrire nato medicament
cheap androxal usa overnight delivery
how to buy androxal cheap fast shipping
ordering flexeril cyclobenzaprine purchase usa
buy cheap flexeril cyclobenzaprine generic efficacy
how to buy dutasteride generic no prescription
order dutasteride cost effectiveness
discount fildena generic fildena
generic fildena in brazil
gabapentin overnight delivery saturday
ordering gabapentin cheap next day delivery
how to buy itraconazole usa where to buy
online order itraconazole generic drug india
how to order staxyn uk online pharmacy
online order staxyn uk sales
foreign drug purchase without prescription avodart
order avodart price prescription
is there a generic xifaxan avaliable in the usa
buying xifaxan generic drug india
generic rifaximin quick shipping
order rifaximin cheap where
donde comprar kamagra en galerias capon
kamagra objednat online s e šekem
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/register?ref=IXBIAFVY
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/register?ref=IXBIAFVY
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/hu/register?ref=IQY5TET4
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.info/register-person?ref=IHJUI7TF